本を読む時「紙の本」、「電子書籍」、「オーディオブック」のどれが良いか、悩むことがありませんか?
また、それぞれの使い分けに悩むこともあると思います。
今回は、そんな時にどのデバイスで読むのが良いか、メリットとデメリットの観点から整理していきたいと思います。
最後に紙の本・電子書籍・オーディオブックそれぞれを「いつ読むと読書が楽しめるか・便利か」の観点でご紹介します。
どの媒体もそれぞれ特徴があります。その特徴を抑えて読書をすればもっと本を読むことを楽しめるはずです。
「紙の本は読みやすいけど、置く場所が無い」
「電子書籍はなんとなく物足りない気がする」
「オーディオブックの使い道がわからない」
そんな疑問を解決していきたいと思います。
- 紙の本のメリットとデメリット【熟読に最適】
- 電子書籍のメリットとデメリット【利便性とコスパ】
- オーディオブックのメリットとデメリット【いつでも読書できる】
- 紙と電子とオーディオブック。おすすめの使い分け
- 紙と電子とオーディオブック。使い分け「まとめ」
紙の本のメリットとデメリット【熟読に最適】

まずは、最もスタンダードな紙の本のメリットとデメリットです。
【紙の本のメリット】
・読みやすい(記憶に定着しやすい)
・さかのぼって読むことができる
・カスタムしやすい
・所有感がある
・購入しやすい
紙の本の最大のメリットは慣れ親しんでいることもあり「読みやすさ」です。また、紙の本は記憶の定着率も高い可能性が示唆されています。
また、ページをめくりやすいのでさかのぼって読んだり、飛ばし読みがしやすいです。
さらに、カスタムしやすいです。ドックイヤーをつけたり、ペンで色をつけたり、付箋を貼りやすいです。
さらに、自宅の本棚に並ぶと所有感もありますし、日本中どこでも購入することができます。
これらが紙の本を読むことのメリットです。
※ちなみに、難しい本を読む切るために5つのアイデアを整理しています。詳細はこちらから
【紙の本のデメリット】
・基本的に定価販売
・場所を取る
・重い、持ち運び性が悪い
・劣化する
一方で紙の本にも、もちろんデメリットがあります。
紙の本では、定価販売が基本です。そのためたくさん本を買うとそれなりにお金がかかります。
また、どうしても場所を取るので、たくさん本を読む人だといつか保管場所に苦労します。※中古で売ってもあまり高く売れないのもあり、処分しにくい。
持ち運びも文庫本や新書であれば苦労しないですが、ハードカバーの本を持ち運ぶのは大変です。毎日本を持ち運ぶ習慣がある人は少ないと思います。
最後に劣化です。汚れや水に弱いですし、日光で日焼けします。適当に保管していると、本が黄色くなってしまいます。もちろん、いつかはボロボロになります。
電子書籍のメリットとデメリット【利便性とコスパ】

【電子書籍のメリット】
・セールがある
・持ち運びしやすい
・劣化しない
・デバイスで共有できる(貸し借りしやすい)
・購入できるタイトルが多い
・すぐに読める
・場所を取らない
電子書籍にはメリットがたくさんあります。
まずは、セールがあることです。場合によっては、比較的新しい本でも半額以下で購入することができます。さらに、Amazonプライム会員特典など、一部無料で読むことができます。
他にも、青空文庫など無料で本を読む方法はたくさんあります。
また、携帯電話やタブレットで読めるので持ち運び性は高いです。電子書籍用端末も非常に軽量なので、毎日持ち運べます。
紙と違って、データのため劣化の懸念もありません。デバイスが壊れてもID・パスワードで再度ダウンロード可能です。
さらに、データはほぼ無限に保管できるので、過去の本でも購入することができます。もちろん、電子化される前の本は読めないので、そこはデメリットです。
データだからこそ、インターネット環境があればすぐに本を読めます。たった数秒待つだけで、新しい本を読むことができるのは、紙の本には無いメリットです。
最後に、保管スペースを取りません。どうしても読書家は家が本だらけになりがちなので、乱読する人には大きなメリットだと思います。
【電子書籍のデメリット】
・紙より読みにくい
・カスタムしにくい
・電池を使う
・所有感が無い
続いて、電子書籍のデメリットです。
もちろん、人によりますが「紙の本が一番読みやすい」と思う人は多いのでは無いでしょうか?
また、データのためカスタマイズ性は低いです。付箋やハイライトをつけることもできますが、紙の方が直観的にできます。
また、当たり前ですが電気を消費します。紙の本は何度読んでも維持費はかかりませんが、電子書籍はわずかに電気代が発生します。もちろん、データ通信費も必要です。
個人的に電子書籍の最大のデメリットは「所有感が無い事」です。
やはり本は並んでいる方が、読んでいる感があります。本がデータで残る便利さと引き換えに、なんとなく寂しさもあります。
オーディオブックのメリットとデメリット【いつでも読書できる】

最後にメリットとデメリットを整理するのは「オーディオブック」です。かなり限定的な使い方になりますが、他には無い魅力があります。
【オーディオブックのメリット】
・ながら聞きが出来る
・目が疲れない
オーディオブックの最大のメリットは「ながら聞き」です。
家事や散歩をしながら本が読める(聞ける)のはありがたいです。もちろん車や電車の移動中でも聞くことができます。
私は散歩が趣味なので、オーディオブックで本を聞きながら散歩できるのは非常にありがたいです。血流量も増えるので集中して聞けます。
また、簡単な家事をしている時も聞けるので、家事の時間を無駄だと思わずに過ごせます。
最後に、目が疲れないのもメリットです。本を読んでいたり、パソコン・スマホ・テレビなどで消耗した目を休めることができます。
【オーディオブックのデメリット】
・価格が高い
・操作性が低い
・聞き逃し
・グラフや図が見えない
・カスタムできない
オーディオブックには、まだまだ多くのデメリットがあると思っています。流通量が増えれば、ある程度緩和するものもあると思います。
まずは、価格が高いことです。もちろん全てが高い訳では無いですが「作者」「出版社」「販売者」に加えて、「朗読する人」にも費用が発生します。
そのため、他の本よりもコストがかかります。普及率も低いため、その分余計に購入費用が高くなる傾向があります
また、音なので操作性は低いです。一ページ前に戻る。○○の内容だけ聞く。という使い方はしにくいです。
さらに、ついついぼーっとした時に聞き逃しがあったり、グラフや図を見ることができないのもデメリットです。
本を読むときはグラフや図に理解を助けてもらうことが多いので、音しかないオーディオブックは、そういった本には適していないです。
最後に、カスタム性も低いです。唯一出来るカスタムは「速度調整」くらいだと思います。
紙と電子とオーディオブック。おすすめの使い分け
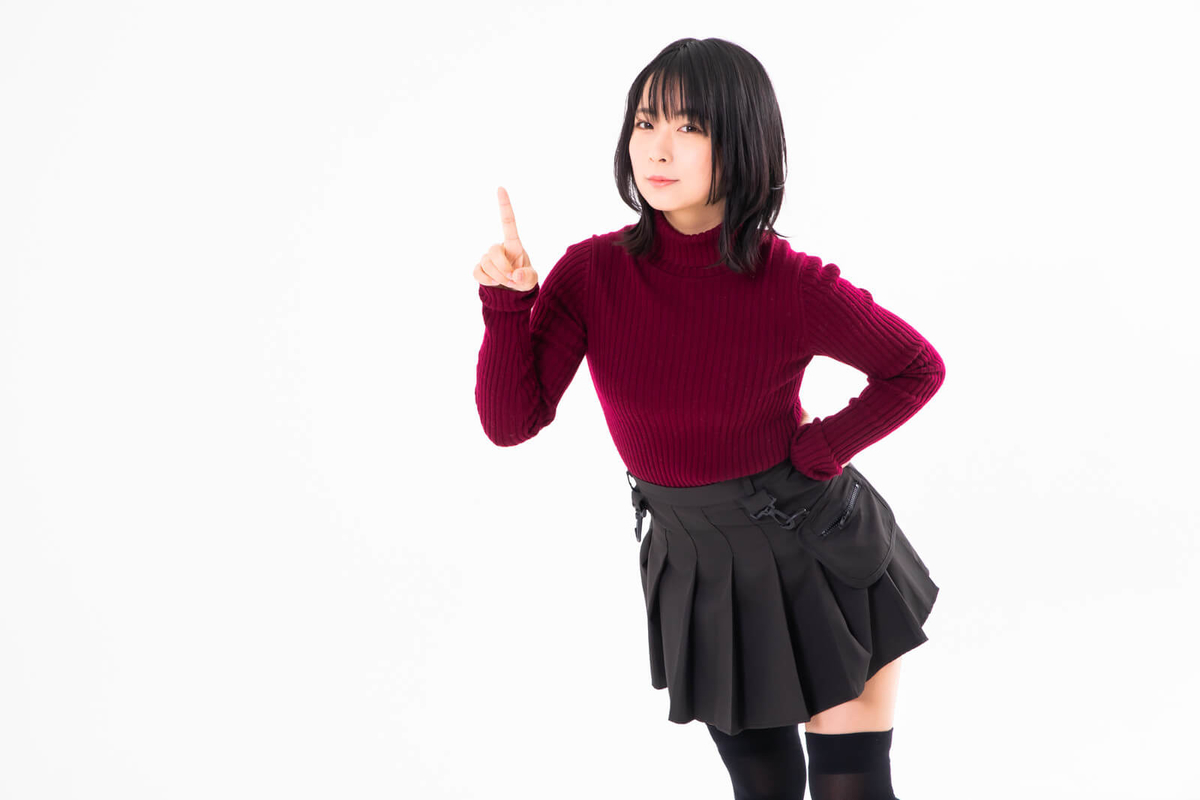
ここまで、それぞれに対してメリットとデメリットを整理してきました。
ここからは、どんな風に使えば読書をもっと楽しめるか。についてご紹介していきます。
それぞれの強みや魅力を活かす読み方が身に付けば、これまで以上に読書を楽しむことができるはずです。
【紙の本がおすすめな場面】
・家でゆっくり本を読む時
・専門書や学術書など読み返したい本を読む時
・難解な本や記憶したい本を読む時
紙の本のメリットは何よりも「読みやすさ」と「読んでいる感」があることです。自宅でコーヒーを飲みながらじっくり読んだり、ソファーに座ってまったり、本を読むのに適しています。
また、何度も読み返す必要があるような本も、紙の本がベストです。正直、予算と場所が許すなら、家で本を読むときは紙の本がベストだと思います。
【電子書籍がおすすめな場面】
・読みたい本がセールになっている時
・外出先や電車での移動中
・お風呂
・一度読めば満足する本
電子書籍の場合は、その利便性を活かすことをおすすめします。
価格的にセールになっていたり、一度読めば充分な本は電子書籍がおすすめです。個人的には電子書籍で読むのは小説がおすすめです。
小説は一部だけ読むことはあまりなく、一度読み始めたら最後まで読み続けることが多いです。そのため、電子書籍でも不便さを感じる場面が少ないです。
さらに、外出先やお風呂でも端末次第では本を読めるのも魅力です。私はお風呂の中や電車では、もっぱら電子書籍を読んでいます。
【オーディオブックがおすすめな場面】
オーディオブックがおすすめな場面は2つです。「散歩中」「家事中」です。
内容が複雑なものは家事をしながら読むことは難しいと思います。そのため、最もおすすめなのは散歩中です。
気持ちよく歩きながら、知識も身に付きます。「なんとなく、やる気が出ないな」と思う時は、散歩しながらのオーディオブックがおすすめです。
私は、Amazonの「Audible」を使っています。月額1,500円で一冊無料です。もちろん、購入もできます。
さらに、ポッドキャストで聞き放題のコンテンツもあります。が、私は利用していません。無料で入手できる情報で言えば、今はYOUTUBEが最強だと思っています。
紙と電子とオーディオブック。使い分け「まとめ」

今回は、紙の本と電子書籍、オーディオブックのメリット/デメリットについての整理と、おすすめの使い分けについてご紹介しました。
この3つを上手に、また自分らしく使い分けできれば、もっともっと本をたくさん読んだり、楽しく読めると思います。
あなたの読書ライフが少しでも良いものになるきっかけになれば、幸いです。
